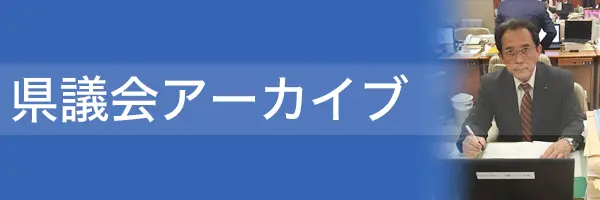◯九十三番(高木ひろし君)
私からは、歳出第九款教育・スポーツ費第四項高等学校費に関わって、県立高校におけるエレベーターの設置について伺います。
二〇二〇年に、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、いわゆるバリアフリー法が改正をされまして、学校がその対象に含まれることになりました。特別支援学校や公立小中学校のバリアフリー化が義務となり、高等学校に関しても、適合努力義務の対象とされたことによりまして、学校施設のバリアフリー化が加速をしてきております。二〇二二年秋には、国連の障害者権利委員会から日本に対して、インクルーシブ教育に向けた勧告が出され、障害のある児童生徒が就学、進学する上で、バリアフリー環境が整っていないことを理由に、これが制限されるようなことがあってはならないということが強い法的な要請ともなってきております。
もともと愛知県においては、今から三十年前、一九九五年に全国に先駆けて、兵庫県、大阪府に続く、人にやさしい街づくりの推進に関する条例を制定いたしました。こうして、バリアフリーの先進県が本県の看板であったはずなのに、愛知県立高校におけるエレベーターの設置率が非常に低い状態が続いていることを私は繰り返しこの県議会でも問題視してまいりました。そして、このことは、障害のある生徒の高校進学を阻む高い壁になっており、教員や職員の障害者雇用の促進の妨げにもなっていることは、改めて指摘するまでもありません。
愛知県の県立高校百五十校中、僅かに九校──パーセンテージにして六%ですが──にしかエレベーターが設置されていないという本県の現状が、他の都道府県に比べてどれほど低いのかという比較データが、このほど明らかになりました。県内の障害者団体の方が全国四十七都道府県教育委員会に電話で問合せを行い、集計された結果によりますと、公立高校のエレベーターの設置率第一位は東京都で八五%、第二位は熊本県、七四%、第三位は大阪府、七三%、第四位、福岡県、六五%、第五位、山梨県、六三%と続き、残念ながら本県の六%という設置率は下位から四番目の低さとなっております。どうしてこのような立ち後れが生じてしまったんでしょうか。
問題の根本には、愛知県人にやさしい街づくりの推進に関する条例、先ほど述べました、これに対する愛知県教委の消極的な姿勢があると思います。同条例では、学校を特定施設としてバリアフリー化の対象の筆頭に掲げ、校舎を新設、建て替えするときにはエレベーターを必ず設置しなければならないとしており、これまで旭丘高校、愛知総合工科高校、愛知商業高校、岡崎商業高校、豊田東高校、安城農林高校、岩津高校、そして桃陵と宝陵という二つの学校に養護学校の高等部が併設されたことによりまして九校に設置されてきております。そして、現在改築中の明和高校、春日井高校、そして高校再編に伴い校舎を増築中の稲沢緑風館高校にもエレベーターが設置されることになっております。これでやっと十二校と数えられます。
しかし、問題は、同条例で定める既存の校舎への増築を含めた適合努力義務についての方針を愛知県教育委員会は持っていないということであります。整備計画の目標すらないのであります。現在、県は、学校施設の長寿命化計画の下で既存校舎の改修を進めていますが、手すりやスロープなどのバリアフリー工事は必要に応じて行っておりますものの、エレベーターの増設は一切行っていないということであります。こうした姿勢は、学校施設のバリアフリー化が法的な義務となり、障害者基本法の改正によってインクルーシブ教育が求められるようになった現在、極めて時代遅れであると言わざるを得ません。
一方、小中学校においては、原則として、車椅子使用などエレベーターを必要とする児童の入学に対応する合理的な配慮として、エレベーター増設が着々と進められております。愛知県内の公立小中学校千三百六十四校中、今日までに三百五校、二二・四%の学校にエレベーターが既に設置されてきております。県内の小中学校におきまして車椅子を使用している児童生徒が一体何人在籍しているのか、この実態を地域ごとに、学年ごとに把握することによって、その多くは順次高校へと進学する時期を迎えるはずであるので、高校におけるエレベーター設置の今後の必要数が推計することができ、計画化の重要な基礎となるはずであります。
そうした観点で、一昨年の議案質疑の中で、私からこの調査を要望し、飯田教育長が実施を約束していただきました。このたび、その結果がまとまったとお聞きをいたしましたので、質問をしたいと思います。
県内の小中学校においてエレベーターを必要とする児童生徒の在籍者数について、調査の結果はどのようになっているのか、お示しください。そして、県立高校へのエレベーターの整備を進めていくために、こうした調査結果を活用していくことが必要と考えますが、教育長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。
◯教育長(飯田靖君)
初めに、県内の小中学校においてエレベーターを必要とする児童生徒数の調査結果についてお答えをいたします。
この調査は、県内の小中学校を対象に、二〇二四年九月一日現在で、常に車椅子を使用している児童生徒数を調べたものでございますが、一人以上在籍をしている市町村は四十五市町村でございました。学年別に見てみますと、小学校一年生から中学校三年生までの各学年に十一人から三十人在籍をしており、合計で、小学校が百五十六人、中学校が四十八人の、全体で二百四人でございました。
次に、調査結果を活用した県立高校へのエレベーターの設置についてお答えをいたします。
議員お示しのとおり、エレベーターが設置済みの県立高校は百五十校のうち九校で、現在建築中の三校を合わせて十二校ございます。また、併設型中高一貫校六校の中学校舎は、バリアフリー法で義務づけられておりますので設置をしてまいります。
エレベーターの設置は、法では、小中学校は義務、高校は努力義務であり、今回の調査で、多くの市町村で小中学校に車椅子を使用している児童生徒がいる現状が分かりました。こうした子供たちが順次県立高校に入学をしてくることを考えますと、高校でも障害のある生徒や車椅子が必要な生徒が、安心をして学べる環境を整えていくことが必要であると考えます。
そこで、エレベーターの設置が進んでいる熊本県や大阪府など先進県の取組状況や、児童生徒の在籍状況を参考に、子供たちのニーズに応えられるよう、検討したいと考えております。
◯九十三番(高木ひろし君)
県内の地域の小中学校に車椅子を使用して通っている子供たちが二百人以上いると。この数字は決して少ない数ではないと思います。この実態を県教委自らの調査で明らかにされたこと自体、一つの大きな前進だと評価しつつ、要望を申し上げたいと思います。
昨年、こんな事例がありました。教員になりたいと強く願っている学力優秀な少女が岡崎市に住んでおりました。大学での教員免許取得を目指して、この少女は県立高校の普通科への進学を希望していました。進行性の難病を患い、電動車椅子を使用している彼女は、母親と共に自宅から通えそうな県立高校四校を訪問いたしまして、学校生活についていろいろと質問しました。この四校はいずれの学校もエレベーターは設置されておりませんでしたので、もし電動車椅子を使用している自分がこの学校に入学できたら、何らかの支援措置や合理的配慮によって、自分もこの学校で学んでいくことができるのでしょうかと問いかけたのであります。返ってきた高校側の答えに彼女は強い失望を感じざるを得ませんでした。本校では今まで車椅子を使用する生徒は一人も受け入れた経験がない。校舎の構造上、一階に教室を設置することができない。校門や駐車場から補助者がいないと校舎に入ることもできない。車椅子対応トイレが現在ない。階段昇降機も現在学校には設置していないなどと、各学校の現状を説明することに終始したそうであります。教育委員会からは、受験上の配慮はされますので、どんな障害をお持ちの方でも受験していただくことは可能ですという案内も受けておりますが、県立高校に自分の居場所が保障されていることを感じることができなかった彼女は、結局、公立高校の受験そのものを諦めてしまったのであります。現在、彼女はある私立高校に通っているそうですが、まだ教員になりたいという情熱を捨てずにいてくれるんだろうかと心配になります。
現在、高校無償化に関する国の動きは急速に進展しつつあり、経済的負担面での公私の格差はほぼ完全に解消されていくことになるでしょう。そうすると、これまで公立の優位が言われてきた愛知県においてすら、設備面で勝る私立高校へと生徒が流れる傾向はますます強まらざるを得ないでしょう。中高一貫校の導入など県立高校の魅力向上に、そしてその改革に様々な取組をされていることを承知しておりますが、バリアフリー化という時代の要請、公的な要請に率先して応えていくことこそ、公立高校のミッションではないでしょうか。エレベーターはその象徴的なものであると考え、私はこだわり続けてきました。これらを必要とする子供たちの存在が今回の調査によって把握できたわけですから、この子供たちのニーズに確実に応えることができるような、公立高校におけるエレベーターの計画的な整備を進めていただけるよう要望して終わります。