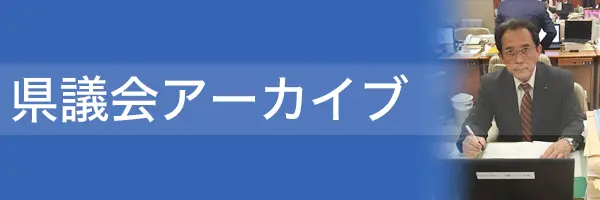◯九十三番(高木ひろし君)
私からは、歳出第四款福祉医療費第九項医薬費のうち、精神障害者地域移行・地域定着支援事業費に関して、精神科病院に入院している方への支援についてお伺いいたします。
二月十二日のNHKのクローズアップ現代で放送された精神疾患六百万人”閉じる家族”をどう支える?という番組がございました。御覧になった方もあるかもしれませんが、改めて急増する精神疾患の患者と、その家族の深刻な実態に迫る番組でありました。
諸外国に比べて異常に多い日本の精神科病床数、そして入院の長期化、そして医療保護入院など、本人の意思に基づかない強制入院制度が強く批判される一方で、精神疾患を持ちながら地域で生きている障害者とその家族の負担が非常に重く、家族が追い詰められている実態がアンケートなどから見えてきました。
鬱病や、鬱と躁を交互に繰り返す双極性、幻覚や幻聴に苦しむ統合失調症、こうした精神疾患の患者を抱えていても、家族が差別や偏見、スティグマを恐れて、周囲にそのことを伝えづらい、支援を求めづらいという、精神疾患特有の事情があります。
こうして、適切な相談先や医療や福祉サービスにたどり着けないで、過度な負担を家族が抱え込んでしまった結果、悲劇的な事態に至るという事例も珍しくありません。
今や二十人に一人は罹患するおそれのある精神疾患、精神障害に対して、これまでのように専ら精神科病院への隔離、収容というような形ではなく、適切な医療を受けながら、地域で自分らしく生きていける地域共生社会に包摂するような取組が求められていると言えます。
その方向性は、高齢者、障害者などの相談や福祉サービスの支援を担う地域包括ケアシステムを精神障害者にも──包括といいますが──にも対応できるようなものにしていこうという動きにも表れております。
こうした中で、二〇二二年に精神保健福祉法が改正をされました。そして、その改正精神保健福祉法に基づいて昨年四月からは、医療保護入院の期間を六か月以内に制限すること、精神科病院内での虐待の禁止と通報の義務化、そして、地域生活への移行──すなわち退院でありますが──これを促進する措置が導入されました。そして、並んで、都道府県による入院者訪問支援事業というのが始まりました。
この入院者訪問支援事業は、大阪における先進的な取組がモデルとなったということを知りまして、その中心となった認定NPO法人大阪精神医療人権センターの活動を私は調査をいたしました。
大阪では一九八〇年代から、精神障害の当事者やその家族、医療福祉従事者、弁護士らがこのセンターを結成いたしまして、精神科病院入院者からの電話や投書による相談、そして訪問活動を通じて、退院支援の取組を続けてまいりましたが、当初は病院によっては、面会を妨害されるなどの壁にもぶち当たることがありました。
こうした事態が大きく進展した契機は、一九九三年に起きた大和川病院事件というものでありました。
これは大和川病院に入院したある患者の死亡が病院側の虐待、暴行によるものであるということが判明をし、この精神科病院の劣悪な医療実態や患者の処遇、はたまた診療報酬の不正受給ということまでもが次々と暴かれて、大きな社会問題となったのであります。
この反省から大阪府では、この告発の中心を担った同大阪精神医療人権センターを中心として、精神科病院協会、精神保健福祉士協会、精神障害当事者や家族の会、そして大阪弁護士会、社会福祉協議会──この中には大阪市成年後見支援センターが含まれております──こうした方々を構成員とする協議会を正式に設置をいたしました。
そして、精神医療オンブズマンと呼ばれる制度が制度化され、療養環境サポーターというような方々が養成されて病院に派遣されるなどの取組が始まってまいりました。
こうして、精神科病院を開かれたものとして、入院患者の声を処遇の改善や退院支援に結びつけていったのであります。
同センターの方にお聞きしますと、しかし、あくまでもこの人権センターの活動の基本は患者の声を聞くということであると言っていらっしゃいました。
その数の広がりは、最近では電話やメール、手紙、そして訪問による面会、こうした形で寄せられる相談、件数にして年間千五百件にも達しておるそうであります。
この数字こそ大阪においてこの精神医療人権センターが勝ち取ってきた患者からの信頼や期待の定着ぶりを表すものだと感じました。
そこで質問であります。
愛知県において今年度から始まった精神科病院で入院者に対する訪問支援員、この役割について、県はどのように考えていらっしゃるんでしょうか。また、精神科病院に入院している方への支援に向けて、今後どのような訪問支援員の養成に取り組んでいかれるのか伺います。
◯保健医療局長(長谷川勢子君)
初めに、入院者訪問支援事業における訪問支援員の役割についてお答えします。
精神科病院に入院している方は、院外の方との面会交流が途絶えやすく、孤独感や日常の困り事を相談することが難しいといった悩みを抱えることがあります。
訪問支援員の役割は、そうした対象の方と会話を交わし、誠実かつ熱心に傾聴し、相手の立場に寄り添うことで、その方の孤独感の軽減や自尊心の醸成を促すとともに、困り事を解消できるよう情報提供を行うことです。
本県では本年度から、精神科病院に派遣された訪問支援員が対象の方と面会交流する入院者訪問支援事業を開始し、これまでに延べ十件の派遣を行いました。
次に、訪問支援員の養成の取組についてお答えします。
本年度は、精神保健福祉士を対象に、精神科病院の現状や入院している方が抱えている課題を理解する講義及び傾聴技術をグループワークによって学ぶ研修を実施し、六十六名の方を訪問支援員として選任しました。
また、対象の方の多様な支援ニーズに応えるには、様々な方に訪問支援員として活躍いただくことは、大変有意義であると考えます。
来年度からは、障害福祉に関する相談支援専門員や精神科病院の入院経験者等にも受講対象を広げることで、より多様な担い手による支援が行えるよう、訪問支援員の養成に努めてまいります。
今後も、精神科病院に入院している方への支援にしっかりと取り組んでまいります。
◯九十三番(高木ひろし君)
それでは要望させていただきたいと思います。
私がなぜこの大阪の取組に着目したかということは、実は去年、この議案質疑で同様のテーマに触れて質問いたしました。
それは、精神科病院に入院している方々の訴えが本当に外部に届いているのか、それが実現されているのかというようなことに関わって、愛知県にも設置されております精神医療審査会に届いた患者の方々からの声がどのように実現をしたか、どういうふうに扱われたかということを、各都道府県や政令市に設置されたこの審査会のデータを調べてみたところから着目したわけです。
愛知県ではこの五年間に遡っても、患者からの退院やら、あるいは処遇の改善の訴えが数十件出されていますが、ほとんどそのうち、それが実現された例が見つからなかったと。精神医療審査会が本当に機能しているのかというふうに疑わざるを得ないような数字でありました。
一方、これはほかの都道府県を見ますと、大阪市などではその認容率、精神医療審査会に患者からの訴えが届けられて、処遇の改善とか退院に関わる要望が実現をする認容率というのが三七・五%。大阪市ですね、審査会。大阪府におきましても一割以上の認容率。
そして、この審査会に持ち込まれる件数自体が極端に多いんです。千二百二十三件、五年間で。これは愛知県の審査会が審査している件数の数倍に上ります。
なぜこんなことが大阪でできているのか、大阪だけが突出して、こうして精神科病院に入院している方の処遇に関するシステムが整って、その声をいろんな形で実現しようという取組が成果を発揮しているのかというところに着目して調べた結果が、この三十年にわたる活動の実績を持つ、大阪の精神医療人権センターでありました。
現在、この国の施策によって、大阪をモデルとする施策によって、全国の都道府県が入院者の支援事業の支援員を養成し、これを派遣するという事業に今年度から取り組んでおります。愛知県も七十数人の支援員の方が養成されたということは、これは大変な前進だと思います。
この方々の活躍にぜひ期待をしたいところでありますけれども、これはやっぱり今までの大阪の経過を見ても分かりますように、なかなか精神科医療の入院者の処遇に関しては、指定医という方の権限が非常に強いわけですね。
指定医の方がこの人は退院してもいいというふうに判断しない限り、本人がいかなる訴えをしようとも、それが審査会でその指定医の判断を覆して、退院ができる、処遇が改善されるということはほとんどないというのが実態であります。
この指定医のみの意見でもって処遇が決まるということに対して、やはり外部からの目を入れる、外部の方が接触をするということが鍵なんですね。
大阪のほうでは、この精神科に入院している方へというこんな分かりやすいパンフレットが全ての大阪府の精神科病院の患者の下に届けられています。
そして、精神科病院には必ず公衆電話が設置されておりまして、これが遮蔽された、プライバシーが保たれるような状態で、外部に、そしてこの人権センターの、そして精神医療審査会の連絡窓口がその電話の横には貼り出してあると、こういう実態があるんですね。
こういった実態にまでたどり着いて初めて、恐らく、本当の入院している方の訴えが実現するような条件が整うのではないかと思います。
これは病院協会、病院側の協力も必要ですし、県として、これはやっぱり国の政策に基づいて、この支援員の方が十分に活動が、成果が出るような形で、この制度を運用していっていただきたい。
そして、愛知県においても、この大阪の人権センターに倣ったようなセンターをつくろうと、NPOとして、こういう動きが今始まっておりまして、私もそれに関わらせていただいておりますけれども、こうした県が養成する支援員の方、そして外部のNPOとしてこの人権センターのような活動をする方、そういった者が連携して、精神科病院に入院しても人権がきちっと守られて、適切な医療と地域生活への権利が守られるという事態に近づくように取組を要望いたしまして、終わります。