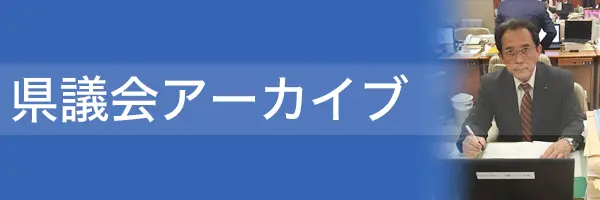【高木ひろし委員】
二つのテーマについて質問する。
一つは、旧優生保護法に係る強制不妊手術の問題に関しては、7月に最高裁判所の判決が出て以来、政府、国会を挙げて、謝罪や補償に取り組んでいる。この件は、9月の一般質問でも取り上げ、県としては決して他人事ではなく、県における審査会が具体的にこの不妊手術の個々の例について実施しているわけであり、その数は愛知県内だけで少なくとも250例以上あったとのことである。
これが、今回の旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者等に対する補償金等の支給等に関する法律の成立により、補償を一人残らず届けなければいけないとなってきており、これは戦後最大の障害者に対する人権侵害事件といった位置づけも与えられているほど重大な事件のため、まず、人権課題としてのこの問題について、人権推進課を所管する本委員会としては、改めて現在どのようにして、人権課題として、あいち人権センターその他で旧優生保護法における強制不妊手術、その根底にある優生思想の根絶について取り組んでいるのか伺う。
【人権推進課長】
本件について、大村秀章知事も9月の定例記者会見で、大きな人権侵害があったと言わざるを得ないとコメントしている。
そうした中、9月の県民環境委員会でも高木ひろし委員から質問があり、その後、旧優生保護法に係る人権課題の解消に資する啓発の図書を3冊購入し、11月から東大手庁舎のあいち人権センターで配架している。引き続き、必要な啓発図書を購入して、啓発に努めていきたい。
また、同じく11月から、当課で実施している人権研修においても、人権意識が希薄な中で行われた不妊手術の強制について触れることとし、人権施策全般を包括する課として、いかに人権が尊重される社会であることが大切かを伝えている。
【高木ひろし委員】
全国的には9月30日に国と原告団が最高裁判所判決に基づいて基本合意書を交わしており、その中では大きく三点の合意がされている。
一つ目は、旧優生保護法被害者の被害の回復に向けた施策、二つ目は、なぜこのような重大な人権侵害が50年にもわたって法律に基づいて行われたのかの真相究明や検証、再発防止のための調査、三つ目は、根底にある優生思想や障害者に対する偏見、差別、これらの根絶に向けて、教育、啓発に対して総合的に検討し、実施するとのことである。
この三点が国と原告団との間で合意されており、また、本県も名古屋高等裁判所において争っていた原告団、尾上夫妻であるが、この裁判に関しても和解が成立した。
これを受けて、11月下旬には、国と同様の確認が取り交わされ、これにより、県としては具体的に、この問題に対する取組をすべき立場に立ったわけであるが、先日この問題で原告団と県の関係部局との間で話合いが行われ、その場には保健医療局のこころの健康推進室が旧優生保護法の問題についての窓口をしていた。
当然これは障害者差別でもあるため、障害福祉課、福祉局も参加していた。学校教育において優生思想が流布された過去の経緯もあるため、教育委員会も参加していたが、そこに人権推進課の姿はなかった。
総合的に検討して取り組まなければいけない旧優生保護法に係る課題に対して、窓口はこころの健康推進室であったとしても、障害福祉課、あるいは教育委員会、当然人権推進課もこれに加わって、教育、啓発の実を上げるために努力すべきではないかと思うが、どうか。県庁内の体制において、この問題の取扱いについて人権推進課はどのような認識でいるのか。
【人権推進課長】
愛知県人権尊重の社会づくり条例においては、第2条のとおり、愛知県は人権施策を実施する責務を有し、国や市町村と連携して、人権施策の推進に努めるものとされており、いずれの課、室においても人権施策を推進することとされている。
こうした中、女性、障害者、高齢者など個別の人権問題に対しては、それぞれ最も関連の深い担当課、室が中心となって取組を進めており、人権推進課は人権条例や、本年3月に策定したあいち人権推進プランを踏まえ、県全体の人権施策の総合的な推進、こちらを図る立場であると考えている。
個別の人権課題の解消に向けた啓発の一例としては、ハンセン病について、担当課が中心となり、ハンセン病を正しく理解するためにリーフレットを作成して、あらゆる機会を通じて、ハンセン病に対する正しい知識の普及啓発活動を進めている。
本県におけるいずれの人権課題も重大な人権課題であると考えている中、当課では、これまでも個別の人権課題に係る団体との話合いには入っていない状況であるが、こうした担当課室と常に情報共有等を行い、共に考えながら、人権課題の解消に向けて取組を進めている。
旧優生保護法に係る人権問題については、国と原告団等との基本合意書に基づく教育、啓発等の諸施策の動向を注視しつつ、本県としても啓発に取り組む必要があるものと認識している。
人権施策の総合的な推進を図る当課としても、国や県の担当局、課室が用意する啓発資料を人権センターで配架し、ウェブページに掲載するとともに、人権研修の場において、人権意識についての重要性について言及するなどにより、関係課室と連携協力しながら、積極的に啓発に取り組んでいきたい。
【高木ひろし委員】
人権問題、啓発を中心に総合的に取り組むと言いながら、個別課題については、それぞれの担当課でと形式的なことを言っているが、やはり福祉あるいは医療、それから教育、それぞれの担当課がそろって、総合的な人権、旧優生保護法の問題、優生思想の撤廃の問題について当事者団体と話し合ってる場に、人権推進課がいないのは不自然である。
これは、人権施策に人権推進課が取り組む形式的なことにこだわり過ぎていると思う。そしてまた、人権推進のプラン、計画があり、これは、愛知県人権尊重の社会づくり条例にも根拠があって取り組んでいるわけで、今年7月頃から大きな国民的テーマとして浮上してきた旧優生保護法の問題は、今後の人権推進プランには入っていないので、具体的な記述として、このプランに付け加える、あるいは人権施策推進審議会で一度議論し、必要な委員を追加する、あるいは人権計画の推進体制の中で優生保護法問題の位置づけを検討し、付け加えるといった措置が必要と思うが、どうか。
【人権推進課長】
高木ひろし委員の述べたとおり、あいち人権推進プランでは、旧優生保護法に係る人権課題についての記載がない。こうしたことから、当課としても何らかの位置づけが必要である。
今後2月頃を予定している直近の愛知県人権施策推進審議会において、旧優生保護法に係る人権課題をプランにどのように位置づけていくべきであるか、委員に意見を聞くことについて、担当課、室と調整を図りながら、進めていきたい。
【高木ひろし委員】
続いて、文化芸術活動に対する補助金の在り方について議論したい。
名古屋市中区大須に、私がよく知っている七ツ寺共同スタジオという、小さいが、なかなかユニークな社会性のあるテーマを取り上げて文化活動を続けているスタジオがある。
今年7月に、ガザ、例のイスラエルとの交戦で、子供や病院や学校等の民間の被害が非常に悲惨な状態にあると問題になっている、この地域の課題を取り上げたガザ・モノローグという独白劇が7月20日、21日の2日間にわたり開催された。これは、6月定例議会で愛知県議会が、ガザにおける停戦を全会一致で採択した直後であったので、私もタイムリーな企画だと思い接していたが、その主催者から聞いたところ、愛知県文化活動事業費補助金の募集があり、応募したとのことであった。
ところが、その選に漏れ、補助金をもらえなかった。どうしてだろうかとの話が私のところへ来た。私も意外に思い、ささやかな取組ではあるが、非常にタイムリーで社会性もある企画だけに、なぜこれが選に漏れたのかをいろいろと調べた。
県はこの愛知県文化活動事業費補助金に対して、申請された事業に対して、どのような過程を経て、補助対象事業を採択し、決めているのか、この仕組みについて説明を求める。
【文化芸術課担当課長(文化芸術)】
文化活動事業費補助金の審査については、2段階で審査を行っている。
まず、第一次審査では、各文化団体から提出された申請書類を基に、外部の有識者で構成される愛知県文化活動事業費補助金企画審査会の専門分野別の6人の委員が、書面審査により審査基準に基づき評価を行っている。
さらに、二次審査では、委員全員が一堂に会し、各委員が書面審査により評価した内容について審議し、予算の範囲内において、評価点の高い事業順に補助対象事業を採択し、その補助額も決定している。
【高木ひろし委員】
この七ツ寺共同スタジオの企画に関わった人は、邪推かもしれないが、イスラエルあるいはハマス、この両方どちらの立場に立つのか国連でも意見が分かれているように、あまりにも社会性を帯びて、政治性もある企画なだけに、社会性、政治性を忌避されて外されたのではないか懸念を持っている。
私は決してそんなことはないと伝えたが、審査会の委員がそれぞれ持ち点を持って、四つの基準に基づいて10点満点で配点した結果、集計して上から点数の高かった方から採用しているとのことで、何か意図的に中身を見て排除していることは決してないと、採択の仕組みは理解したが、この審査会の委員は、どのように選考されているのか。
【文化芸術課担当課長(文化芸術)】
審査会においては、各文化団体からの申請に対し、公正かつ公平に審査を実施するため、外部委員による審査方式を導入し、委員には専門分野に精通し、豊富な知識を有する者が就任している。
委員の候補者は、日頃から音楽、芸術、舞踏、技術などの専門家に接する機会の多い愛知県美術館や公益財団法人愛知県文化振興事業団から、委員にふさわしい者を推薦してもらうほか、現在就任している委員からも意見を聴取し、県において、これらの候補者の中から職や経歴などを考慮して決定している。
【高木ひろし委員】
企画審査委員会の委員の名簿を見ると、確かに私も知っているような、それぞれの分野で立派な学識を持つ人が委員に名を連ねているので、妥当な結果だろうと思う。ちなみに、今年度の企画提案事業では申請が何件あり、そのうちどれぐらい採択され、どういったものが採択されたのか、特徴的な事業でもよいので紹介してほしい。
【文化芸術課担当課長(文化芸術)】
本年度文化活動事業費補助金の企画提案事業に対しては、54件の申請があり、このうち21件を補助対象事業として採択した。
このうち分野別の採択数は、音楽が5件、演劇、舞踏がそれぞれ6件、美術が2件、メディア芸術、文学がそれぞれ1件である。
採択された事業の具体的な取組であるが、音楽では、未就学児や大人を対象としたグリム童話をオペラで上演する事業、演劇では、後世に戦争体験や自由と平和な日々の尊さを朗読劇で伝える事業、舞踏では、独特の身体表現スタイルによるジャズ舞踏を上演する事業、さらに美術では、VR技術を活用し、新たなアート作品を作り出す事業などである。
【高木ひろし委員】
今聞いただけでも、それぞれ採択された事業は、立派な価値ある活動であると理解した。しかし、改めて思うのは、申請件数が54件もあるのに、その半分以下しか採択ができないのは、予算規模があまりにも乏しいのではないか。文化活動事業費補助金制度は、30年以上前に県で始まっているが、どのような金額の推移になっているのか。
【文化芸術課担当課長(文化芸術)】
文化活動事業費補助金については、1991年度の県民の自主的、自発的な文化活動を支援するための補助制度を創設し、その財源は、同年度に創設した文化振興基金への愛知県の出資金100億円の運用費の一部を充てることとし、制度創設当初の予算額は2億5,000万円であった。
その後、景気後退や日銀のマイナス金利導入など、社会経済状況の変化により、運用益は大幅に減少したことから、予算額については、年度ごとの変動はあるものの、減少傾向が続き、2017年度以降は2,500万円をベースに措置している。
【高木ひろし委員】
今の説明のように、1991年当時の鈴木礼治知事の英断により、愛知芸術文化センターという立派な拠点は作られた。
しかも、補助金も出して、地元の芸術文化活動を大いに奨励して、愛知芸術文化センターを使って大いに芸術文化の盛んな地域へと、こうした考えで2億5,000万を毎年投じていたものが、現在その10分の1に縮んでしまっている。
この間には、運用益が出なくなっただとか、金利の情勢だとか、途中2000年頃に財政危機があって、非常に大きな補助金がそれぞれ大幅にカットされ、それ以降復元してない経緯がある。国際芸術祭の開催や、海外の有名な前衛芸術家の招待に大変な労力や予算を投じることも結構だと思うが、やはり肝腎なのは県内の、地域の芸術文化活動を担っている人たちにエンカレッジして、手助けすることが基本ではないか。
先ほどの議案で、愛知芸術文化センターの運用を大幅に見直し、民間事業者の運用によって節約できるとの話もあったが、その一部でも、そういう地域の活動に対して振り向けると思う。
2,500万円程度で50数件も応募があるのに、その半分も採用されないのは、あまりにも寂しい実態だと思うので、これは要望にとどめるが、今後の愛知県の文化芸術の振興のために、地域のささやかな活動かもしれないが、そういった芽を育てるための予算制度の拡大を今後考えてもらうことを要望する。