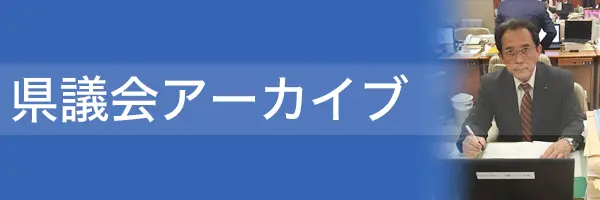【高木ひろし委員】
税以外の債権の収入未済額について伺う。
このテーマについては、令和4年度に包括外部監査が行われており、包括外部監査法人の弁護士の田口勤先生が、未収金の解消に向けた取組の対象となり得る債権を中心に、債権の管理・回収の在り方の一般ルールをどう整理すべきか報告している。非常に重要なテーマだと思う。債権の管理・回収に関して、具体的な問題提起がされており、複数の局にまたがる全庁的な問題として不納欠損処分の取扱いを県で統一するべきであるなどの意見が示されている。回収見込みのない債権について、効率的でないような業務を延々と行っているのは非効率であって、今まで特に回収一本槍だったのに対して、一定のルールに基づいて、放棄や不納欠損処分することによって効率化を図るという観点が示されている。非常に大事な議論だと思う。
総務局として、この包括外部監査の結果をどのように受け止めて、税外債権の債権回収に関するルールづくりについてどのような取組をしたのか伺う。
【資金企画課長】
税外債権の管理・回収に関して、令和4年度の包括外部監査において、債権放棄の円滑化や不納欠損処分の取扱いの統一などについて意見があり、総務局としても、全庁的な対策について現在検討を進めている。
県の債権管理は、公平公正な負担の観点が重要であるが、一方で、適正な債権管理・回収業務を行ってもなお回収可能性のない債権は、事務の効率性や人的資源の有効活用の観点から、一定の規準の下で整理することも必要であると考えている。
そこで、包括外部監査での意見も踏まえて、回収可能性がない債権についての債権放棄や不納欠損処分の統一的な基準を作成するとともに、あわせて、債権放棄または不納欠損処分までに行うべき債権回収手続の標準的な手順・手法を整理して、2024年度中に各局に周知していきたいと考えている。こうした取組を通じて、さらに適正な債権管理・回収に取り組んでいきたい。
【高木ひろし委員】
要望になるが、包括外部監査の報告書によると、県における税外債権の収入未済額は、このところ60億円程度であり、増減がない状態である。新たな収入未済に組み込まれる金額と、回収した収入未済金の金額が相殺され、結局60億円程度の未済額が毎年存在している状況だと思われる。
これは、税における処理の方針と基本的には同じ考え方ではあるが、中身を見ると、高等学校等奨学金貸付金のように、教育の機会均等や、憲法に基づく文化的な最低限度の生活を保障するために貸与したものの回収がある。これは一般的な税の回収とは異なる、質的な判断も必要になると思う。
そのため、各局が所管する債権にはいろいろな種類があり、高等学校等奨学金貸付金など、いろいろな課題があるため、とにかく回収一本のやり方だけではなく、行政の効率化の観点から、あるいは福祉的な配慮の面からも、債権の放棄や、不納欠損処理を行うよう、総務局において全体的なルールをまず定めてもらい、それを各局がマニュアル化して取り組んでいくことが必要だと思うので、ぜひ今年度も引き続き検討してもらいたい。先日も専門家によるヒアリングの席で傍聴させてもらったが、この作業を急いでもらい、今年度、このルールが早く示され、各局のマニュアルに生かしてもらうようにお願いする。
次に、決算に関する報告書、17ページに県会議員選挙のうち、選挙の執行費用について伺う。
これは令和5年度の選挙費として計上しているだけではなく、4月に執行された選挙である第20回の県会議員選挙の費用も含まれていると思う。そのため、予算額、決算額及びその差額について、第20回の県会議員選挙に係る費用と、4年前の第19回の県会議員選挙に係る費用との比較において、どのような状況になっているのか。
【選挙管理委員会事務局次長】
令和5年執行の第20回の選挙では、令和4年度補正予算及び令和5年度当初予算の合計が約25億7,816万円であったのに対して、2か年度分の決算の合計額は約15億6,951万円で、差額は約10億864万円となっている。
また、平成31年4月執行の第19回の選挙では、平成30年度補正予算及び平成31年度当初予算の合計が約22億6,667万円であったのに対して、2か年度分の決算額の合計は約13億5,236万円で、差額は約9億1,431万円となっている。
【高木ひろし委員】
約4割に及ぶ費用が不用額として生じているが、これだけ大きな差額が予算と決算の間に生じている理由は何か。
【選挙管理委員会事務局次長】
差額が大きく生じた理由として、一点目に無投票となった選挙区が多かったことが挙げられる。令和5年4月執行の選挙では、55選挙区のうち24選挙区が、平成31年4月執行の選挙では、55選挙区のうち26選挙区が無投票となっている。無投票となった選挙区の市区町村においては、投票所経費や開票所経費などが不用となったことにより、予算額との差が生じている。
また二点目として、候補者数が想定数を下回ったことが挙げられる。令和5年4月執行の選挙の候補者数は146人、平成31年4月執行の選挙の候補者数は138人であり、それぞれ予算編成時において想定した候補者数を下回ったことにより、候補者の選挙運動に要した費用を公費で負担する選挙公営費について、予算額との差が生じている。
【高木ひろし委員】
この大きな不用額が生じている事態は、選挙のあるべき姿からして、決して望ましいことではない。大きな不用額が生じた理由について無投票の選挙区の率が高いとのことだが、全国的に見ても、愛知県議会議員選挙は、非常に高い部類に入っている。要因はいろいろとあるため、様々な角度から議論されるべきだと思う。
昨年の第20回の県会議員選挙は、投票率が過去最低であり不名誉なものであった。投票率の向上のために、県はいろいろな工夫をしていると思うが、令和5年度の選挙の執行に当たっては、投票率の向上のためにどのような工夫をしたのか。
【選挙管理委員会事務局次長】
投票率の低下は、県選挙管理委員会においても危機感を持っており、投票率向上のためには、啓発活動だけでなく、有権者がより投票しやすい環境を整備することが重要である。その取組の一つとして、県選挙管理委員会では、選挙が執行される際に、市区町村の選挙管理委員会に対して、期日前投票所の増設を呼びかけており、特に利便性の高い商業施設等への期日前投票所の設置、バスなどを利用して複数の箇所を巡回する移動期日前投票所の設置など、投票環境の向上について積極的に検討してもらうよう、必要な助言を行っている。
令和5年執行の選挙では、無投票になった市区町村も含めて、県内で165か所の期日前投票所が設けられており、平成31年執行の選挙の142か所と比べて23か所増えている。
【高木ひろし委員】
要望になるが、投票率の向上のために投票年齢が引き下げられて、18歳から投票できることになり、最初は投票率が上がった。しかし、その後かなり落ち込んだ状態が続いている。
こうした学生などの若い人の投票率をいかに上げるかという課題と、高齢化が非常に進み、自力で投票所に行くことや認知症などで投票が非常に困難な状態になっている人が沢山いる課題がある。
郵便投票や投票時の職員による代筆など、いろいろな配慮をしているが、決して利用しやすいとはいえないため、身体や文字を書くことが不自由になり、認知能力が低下した人にも、投票がしやすい措置はさらに充実されるべきだと考えているので、工夫を重ねてもらうよう要望する。