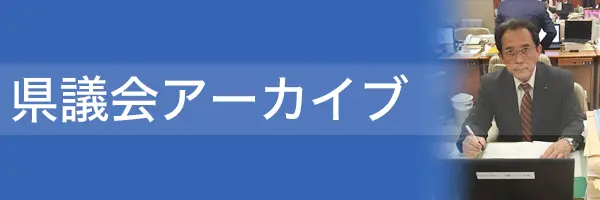【高木ひろし委員】
決算に関する報告書の345ページ、高等学校整備事業費について、昨年度の本会議の議案質疑で高等学校のバリアフリー化について教育長に質問したことを踏まえて、幾つか確認する。
まず、令和5年度の事業費の中で、県立高校150校のエレベーターの設置を含むバリアフリー化がどのように進んだのか伺う。
【財務施設課担当課長(整備)】
県立高校のバリアフリー化については、県立学校施設長寿命化計画に基づく改修工事の中で、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に適合するよう手すりやスロープを設置している。また、これとは別に身体に障害がある生徒の入学等に当たり、昨年度は生徒本人や保護者からの要望に基づき、春日井西高校をはじめ4校へ手すりを設置し、また県立小牧南高校をはじめ3校へスロープを設置した。
なお、エレベーターの設置については、校舎の新築・増改築の際に、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に合わせて設置をしているため、現在県立高校150校のうち9校に設置しているが、昨年度に設置した実績はない。
【高木ひろし委員】
県内の公立小中学校においても、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律、通称バリアフリー法に基づいてエレベーターの設置が義務化され、整備が進んできていると思うが、県内の公立の小中学校におけるエレベーターの設置状況はどうか。
【財務施設課担当課長(整備)】
県内の公立小中学校におけるエレベーターの設置状況について、本年5月1日現在で305校に設置されており、設置率は22.4パーセントとなっている。なお、昨年度は287校に設置され、設置率は21パーセントであったため、この1年間で設置校は18校、設置率にして1.4ポイント増加している。
【高木ひろし委員】
県立高校150校のうち現在は9校に設置済になるため、設置率にすると6パーセントである。
県内の公立小中学校は全体で何校あるのか。
【財務施設課担当課長(整備)】
小中学校合わせて1,364校である。
【高木ひろし委員】
小中学校においては既に2割以上の学校にエレベーターが設置されているが、県立高校ではまだ一桁の6パーセントにとどまっており、随分差がついている。なぜこうした差ができたのかについても論じたいが、まず、今後の県立高校のエレベーター設置に関する目標、計画はどうなっているのか。
【財務施設課担当課長(整備)】
県立高校へのエレベーター設置については、原則、人にやさしい街づくりの推進に関する条例に基づき、3階以上かつ延床面積2,000平方メートル以上の建物の新増改築を行う際に設置する。これにより、現在改築を進めている県立明和高校、県立春日井高校の校舎、高校再編に伴い校舎を増築している県立稲沢緑風館高校の3校に4基のエレベーターを設置する予定としている。
【高木ひろし委員】
3校にエレベーター4基の設置を計画しており、これができたとしても合わせて12校であり、設置率は8パーセントである。バリアフリー法で小中学校はエレベーターの設置が義務化されている。高校に関しても適合努力義務が課されており、設置してもしなくてもいいというものではない。適合努力義務が今のような状況の愛知県における県立高校においては、答弁にあったように、人にやさしい街づくりの推進に関する条例で新しい建物を建てたり、改築するときにはエレベーターを設置するという原則であり、建物全体としては長寿命化でできるだけ全面改築を避けながら長く使う方針である。全面改築という方法は絞られてくる。そうすると、必然的にエレベーターの設置のテンポも遅くなる。エレベーター設置はバリアフリー法に定められた適合努力義務であり、小中学校などは国が4割設置を目標にやっているため、県立高校における現在までのエレベーターの設置に関するやり方は、基本的に問題があるのではないかと思っている。
名古屋市も小中学校のエレベーターの設置数が年々増えており、最新の数字だと小中学校合わせて372校中の78校にエレベーターが設置されたと聞いている。設置率にすると21パーセントである。名古屋市はどういう考え方でエレベーターを整備しているかというと、ニーズ発生主義である。下肢に障害があり車椅子を利用している、ストレッチャーに乗ったままでしか移動できない、エレベーターが必要な児童が入学する可能性が出てきたときに予算化に着手する。
そして、その児童が入学する際、あるいは入学した後に、時間を置かずにエレベーターが設置されるということを積み上げてきた結果が今の78校である。県は名古屋市の考え方とは異なる。ニーズのあるなしではなく、新築・改築の場合だけエレベーターを設置することで、新築・改築はなるべくせず現有の建物を長寿命化させようという方針であるため、これから差は広がっていく。
令和5年の2月定例議会で質問したが、県内の小中学校に在籍するエレベーターを必要とする生徒は一定程度存在していることはある程度把握されている。何年か後に高校へ進学する時期を迎えると、高校ではその生徒を受け入れることとなり、義務教育課程に存在するエレベーターを必要としている生徒の実態を県が把握すれば、どこの高校に行くかは分からないが、これを基にして何年後には何基ぐらい必要になるというような、総量としてどれぐらいのペースで増やさなければならないのかという計画の根拠にはなり得る。教育長は国の全国調査に合わせて調べてみると答弁していたが、その調査はどうなっているか。
【財務施設課担当課長(整備)】
文部科学省の全国調査として、今年度、学校施設のバリアフリー化に関する実態調査が、国公立の小中学校及び特別支援学校を対象に行われている。この調査に合わせて、義務教育課程に在籍するエレベーターを必要とする障害のある児童生徒数についても、現在市町村教育委員会に対して県独自で調査を行っている。
【高木ひろし委員】
この件に関しては、重ねての要望になるが、エレベーターの設置を計画化することが適合努力義務の具体的な中身だと思うため、新築や改築のときが来たら実施するというのではなく、何年度までに何基は設置していくといった具体的な形にしなければならない。どの地域に存在する児童生徒が通う可能性があるか、あるいは実際に入学したことに対して早急に措置を進めていくという考え方に転換していかなければいけない。
次に、障害者雇用率の問題について、これは、水増しというと教育委員会としては厳しい言い方になるかもしれないが、計算方法によっては愛知県、特に教育委員会における障害者雇用率の達成が大幅に不足していることが数年前に明らかになった。その後について伺うが、決算に関する報告書326ページ、教職員人事費に令和5年度の教職員の採用選考試験のことが載っている。そこで伺うが、令和5年度採用の教員採用選考試験における障害者選考の志願者数と採用結果はどうであったのか。また、非常勤職員を含めた障害者全体の令和5年度の採用数はどうであったのか。
【教職員課担当課長(県立学校人事)】
2023年度採用の教員採用選考試験において、25人の志願者がおり、そのうち6人が採用となっている。また、非常勤職員を含めた障害者全体の2023年度の採用数は107人となっている。
【高木ひろし委員】
雇用率は計算が難しく、単純にその人数ではない。そのため、法定雇用率が、現在、教育委員会において2.5パーセントまで上がってきていると思うが、私が数年前に質問したときは1.17パーセントという数字であった。今年度の採用を含めていろいろ努力してもらっている。令和5年度6月に障害者雇用率の調査をして、この数字が12月にいつも発表される。障害者雇用率は何パーセントになったのか。
【教職員課担当課長(県立学校人事)】
2024年度の障害者雇用全体の実人数は456人であり、これを障害者雇用率算定のため労働時間や障害の種類、重度に応じて換算した人数は535人となる。その結果、障害者雇用率は1.63パーセントであった。
【高木ひろし委員】
はっきり言ってまだまだ道のりは遠いといえる。目標とする法定雇用率は2.7パーセントから2.9パーセントとどんどん上がっていく。目標とする数値がどんどん上がっていくのに、実雇用率の改善については全然追いついていない。愛知労働局からもいろいろと指導や指摘を受けていると思うが、法定雇用率の達成を目指して、今後の障害者雇用をどう進めようとしているのか。
【教職員課担当課長(県立学校人事)】
障害者の法定雇用率について、県教育委員会としては、できるだけ早期に達成しなければならない。しかしながら、教員として採用するには教員免許が必要であり、教員の中で障害者を大量に採用するというのはなかなか難しい面がある。したがって、教員以外の採用を増やす必要がある。そのため、事務職員や実習助手の障害者枠に加え、令和2年度からは県立学校において、令和4年度からは小中学校において障害者手帳を持つ校務補助員を採用しており、令和5年度には合わせて94人を採用し、校務補助員全体で200人を雇用した。
校務補助員を雇用している学校からは、一つ一つの作業が丁寧である、時間のかかる印刷作業なども任せることができて助かっているといった声が届いており、雇用していない市町村に対し、こういった声を周知していきたい。できるだけ早期に法定雇用率を達成できるよう、今後も着実に障害者雇用の拡大に取り組んでいく。
【高木ひろし委員】
この問題に関する要望だが、先ほど質問した学校がバリアフリーになっていることと、障害のある生徒が入学してくる、あるいは障害のある生徒や補助員が勤務できることは関係があると思う。バリアフリーが整っていない学校に障害のある生徒が入学することも難しく、採用するにしてもどこの学校で働いてもらうかについては、整備面で壁ができている。
したがって、教職員の話で教員免許を持っている障害のある人が少ないという話があったが、これは学校の整備面と関係がある。高校から大学と通うことが障害を持った人にも可能な条件を整えないと免許を持った障害のある人が増えてこないことになる。自然現象のように教員の免許を持った障害のある人が少ないというが、その原因は学校がバリアフリーになっていないことにある。
よって、単にバリアフリー法だけではなくて、障害者の雇用均等を目指した障害者雇用促進法における法定雇用率の大幅未達成と、両方をにらんで、愛知県の高等学校に障害のある能力、意欲のある人が進学できて、そして教員免許を取得して、愛知県の教員として働いてもらえるように、そしてそういった人が働けるような環境を計画的に順次整えていけるように取り組んでいかないと、永遠に達成できないと思う。その点について中期的な目標を持って取り組んでもらうことを要望する。
決算に関する報告書359ページに、学校給食振興事業費があり、学校給食物資検査委託費がある。まずこの費目に上がっている検査を委託して給食材料等の安全性に関する検査を実施したとあるが、検査の結果はどういった結果になったのか。
【保健体育課担当課長(保健体育)】
県立学校で実施している検査については、残留農薬検査とO157検査になる。これらについて検査を実施したが、全て国の基準内に収まっており、O157等については検出されていない。
【高木ひろし委員】
学校給食に関しては、さきの総選挙においても学校給食を国の責任において無償化すべきだという政策を各党が掲げており、特に義務教育課程に関しては全国一律にすべきだと思うが、それを待つまでもなく愛知県内の各市町村において、100パーセント無償化又は一部無償化によって給食費の負担を軽減する動きが相当出てきている。これは、今どれくらいの自治体に広がっているのか。
【保健体育課担当課長(保健体育)】
小中学校の給食費無償化の状況であるが、本年6月現在、津島市、豊田市、安城市、みよし市、飛島村、豊根村の6市村において小中学校の給食費の完全無償化が実施されている。
また、期間や対象を限定して一部無償化を実施している市町が11市町あり、これらを合わせると17市町村である。
【高木ひろし委員】
全国的にも大体3分の1の市町村で既に給食費の完全無償化ないしは一部無償化が実現している。この問題については、例えばこれを県費で全部やるべきだとの請願なども出ているが、県費で無償化することになると、どれぐらいの県費が必要になるのか試算はしているか。
【保健体育課担当課長(保健体育)】
名古屋市を含めた県内の公立小中学校の給食費を無償化するための経費を試算すると、毎年およそ320億円が必要になると見込んでいる。
【高木ひろし委員】
相当な金額であるため、私としては国において措置するように、県としても働きかけていくべきだと考えるので、これを要望とさせてもらう。
次に、令和5年度愛知県歳入歳出決算及び美術品等取得基金運用状況の審査意見書の41ページの下段に、高等学校等奨学事業貸付金収入における収入未済額の記載がある。これは約8億4,800万円であるが、審査意見書の43ページを見ると、8億円前後の未済額はこのところ変わらず、毎年減りも増えもしないという状況が続いている。県としてはこの奨学金の未済額を返済してもらう必要があるが、回収のために手は打っているのか。
【高等学校教育課担当課長(振興・奨学)】
滞納者に対して、初めのうちは職員による文書、電話、訪問による督促を行っている。滞納期間が1年以上となった場合は債権回収業務を弁護士法人等の債権回収業者に委託し、回収に努めている。
また、特段の事情もなく全く返還の意思を示さない長期滞納者については、6月及び12月定例議会の議決を経て奨学金貸付金返還請求事件に係る訴えの提起を行っている。一方で、経済状況により返還が困難な場合について、奨学生や連帯保証人に対して生活状況を聞き取り、1回の返済額を少額とする分割返還を提案するなどの負担軽減を図る取組を行っている。
【高木ひろし委員】
この未済額をどうするかについては、外部委託を既に平成24年からしているが、それによって回収率が特に上がったわけではないように見える。一方で、令和5年度愛知県財務諸表(一般会計局別、管理事業別)(7)の46ページを見ると就学支援事業の中で長期貸付金が貸倒引当金に400万円計上されており、返済免除という措置を執っているケースもある。どういう場合に返済免除になるのか。
【高等学校教育課担当課長(振興・奨学)】
奨学金の事業については、死亡等により返還を免除する場合と、就学が困難になった場合に限る。
【高木ひろし委員】
就学が困難になった場合というのは、どういうことか。
【高等学校教育課担当課長(振興・奨学)】
休学等をした場合、または就職後働けない状況になった場合に限り返還を免除している。
【高木ひろし委員】
最近、教育無償化が各党共通して大きな政治課題になってきている。奨学金についても、昔は貸与型、いわゆる教育ローンが普通であったが、返済の必要のない給付型の奨学金をどんどん増やそうという動きになってきている。そうすると、貸与型の奨学金については、貸したのだから返すことは当然であるが、もともと就学が困難な経済事情にある人に貸し付けており、卒業してもなかなか定職にも就けず、不正規雇用で収入も少ない人が非常に多い。
そのため、私は亡くなった人や途中で就学ができなくなった場合だけ返済免除というのではなく、もう少し弾力的に生活の実態に着目し、実態をある程度把握して処理すべきと考えている。悪意を持って返済しない人は良くないことは確かだが、債権放棄や不納処理などいろいろな方法がある。しかし、その基準がないため、裁判にまで訴えて取り立てようとしている。これは法律に沿ってやっているので仕方がないが、職員にとっても負担になるし、効率が悪い。
それをやって滞納金を回収できればまだよいが、全然回収できないのに形式的に裁判所に訴えることまでしている。収入未済額が8億円程度残っている状況は、実態に合わせて返済の免除をするような形でルールを変えなければならない可能性もあるため、ぜひ検討してもらいたい。