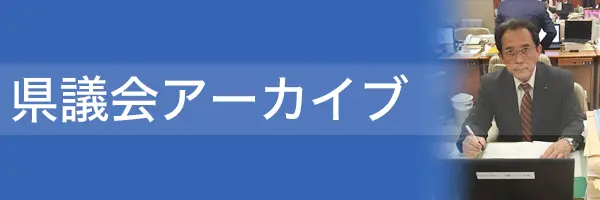【高木ひろし委員】
私からは、令和5年度決算に関する報告書311ページ、住宅総務費のうち公共住宅事業費に関連して伺う。愛知県住宅供給公社の問題である。
愛知県住宅供給公社は、地方住宅供給公社法に基づいて設立され、県の住宅施策を補完する役割を担っているが、その一つとして、住宅供給公社が自ら管理する賃貸住宅を供給している。
現在、公社賃貸住宅の住宅数、管理戸数及び入居状況、入居率はどのようになっているのか。
【県営住宅管理室担当課長(県営住宅)】
令和6年10月1日現在、愛知県住宅供給公社の賃貸住宅は、48住宅である。管理戸数は4,175戸であり、このうち入居しているのは3,070戸で、入居率は73.5パーセントとなっている。
【高木ひろし委員】
入居率が73パーセントは、相当低い数字と言わざるを得ない。このように3割近くが空き家になっていることは、どのようなことが原因と考えているのか。
【県営住宅管理室担当課長(県営住宅)】
愛知県住宅供給公社の賃貸住宅のうち、昭和60年代以降に建設した住宅の入居率は、95パーセントとなっている。一方で、昭和50年代以前に建設し、建設から40年以上が経過した住宅は、エレベーターが設置されていない、住宅の設備が古いなどにより、入居率は低くなっている。
なお、愛知県住宅供給公社では、借地により賃貸住宅事業を行っている住宅について、順次、土地の返還を進めていくこととしており、現在、一部の住宅では、新たな入居者の募集を停止している。
【高木ひろし委員】
私の地元瑞穂区でも、竹田住宅という昭和20年代に建設された古い住宅供給公社の住宅が2棟あったが、本年取壊しになり、今、更地になっている。入居率は悪くなかったが、4階建てであり、エレベーターがなく、住んでいる高齢者は、非常に不便を感じていた。
公営住宅は、県の保有資産として貴重な住宅でもある。空き家を解消して、少しでも入居を促進するために、どのような対策を行っているのか。
【県営住宅管理室担当課長(県営住宅)】
愛知県住宅供給公社では、公社賃貸住宅の入居促進を図るため、間取り変更や台所、給湯設備の更新を中心としたリノベーション工事を実施するとともに、入居者がDIYにより模様替えをすることができる部屋も用意している。
また、一部住宅では、家賃の1か月分を無料とするフリーレントや、新婚、子育て世帯向けに家賃を10パーセント減額する制度など、ソフト面での対策も併せて行っている。
また、空き住戸が多く生じていた住宅で、サービス付き高齢者向け住宅などの供給を目的として、社会福祉法人などの事業者に、定期借家契約によって長期間、空き住戸を一括して貸し付ける取組を行っている。
【高木ひろし委員】
大曽根住宅という名古屋市内の大曽根駅からほど近く、交通の便は悪くないところに大規模な公社住宅があり、交通の便がいい割には空き家率が非常に多かった。
ここは、数年前から事業者が間に入り、まとめて空き家を借り上げ、サービス付き高齢者住宅として、高齢者向けのサービスを付加して貸し出すという事業が行われており、300戸近い空き家が一挙に解消し、利用者にも大変喜ばれている。こうした取組は非常に参考になる。
公社住宅は、公営住宅である県営住宅と違い、家賃の設定や使い方に制約がないので、一般の民間住宅と同じような設備に替えたり、家賃設定を変えるなど、いろいろな余地がある。古くなった住宅は取り壊すだけなく、その中でも、交通の便がよい住宅など活用し得るものは、リノベーションや高齢者や障害者にも利用しやすい附帯工事を施すことによって、まだまだ活用できる余地は十分ある。
こうした特徴を生かして、県営住宅ではカバーし切れない部分を、有用な民間住宅とは違う、公共的な住宅供給の在り方をさらに検討を進めてもらい、大曽根住宅のような事例をさらに増やしてもらうよう要望する。
続いて、決算に関する報告書312ページに公営住宅建設費について伺う。
県営住宅には、かねてより問題になっているが、浴槽や風呂釜がついていない住宅がまだ数多くある。
こうした住宅は、かなり古い時期に建った住宅が多いが、入居者が風呂設備を自己負担で設置して入居する形になっており、これが一種の言わばこの入居時の敷金みたいな形になって、入居するときに風呂釜を20万円程度で、自分で購入して設置することになっている。
風呂がなくてもよいという人はなかなかいないと思う。県営住宅の空き家が埋まらないというのは、理由のあることだと思う。県営住宅は、住宅に困窮する低額所得者のための住宅であるが、低額所得者にとって風呂設備の設置の負担は、決して小さくないと思う。
県営住宅で建設時に風呂設備を設置し供給を始めたのは、いつからなのか。
【公営住宅課担当課長(建設・改善)】
昭和60年度以前に管理開始した住宅には、浴室はあったが、風呂釜、風呂桶などの風呂設備は、入居者が設置することとしていた。
昭和61年4月1日以降に管理開始した全ての新築住宅に風呂設備を設置している。
【高木ひろし委員】
建設時には、風呂設備を設置していなかったが、後から県が風呂設備を設置したという住宅はどれぐらいの戸数があるのか。
【公営住宅課担当課長(建設・改善)】
平成26年度から県において風呂設備のない既存住戸に風呂設備を設置しており、昨年度までに32住宅、480戸に設置した。
【高木ひろし委員】
県営住宅の募集において、風呂設備を設置していない住宅は、先着順の募集案内を見ると結構多い。
風呂設備を設置していない住宅が空き家になって、先着順の受付の対象になっているが、こういった風呂設備を設置していない住宅は今後どのように対応するのか。
【公営住宅課担当課長(建設・改善)】
風呂設備のない老朽化した県営住宅については、建替事業の対象となったものは、新たに建設する住宅に風呂設備が設置されることとなる。
また、当面、建替事業の対象となっていない風呂設備のない住宅についても、順次、風呂設備を設置しており、令和6年度においては、既存住棟の50戸に風呂設備を設置する予定である。
今後においても、引き続き既存住棟への風呂設備の設置を進めていく。
【高木ひろし委員】
同じく県営住宅に関して、もう一点伺う。
決算に関する報告書390ページに県営住宅管理事業特別会計、県営住宅管理運営事業費があるが、県営住宅では入居者の高齢化などに伴って、入居者が組織する自治会が入居者から徴収するエレベーターなどの電気料などの共益費について、その徴収作業が高齢化した自治会役員の負担になっていた。このため、令和2年度から県が共益費の一部を附帯設備使用料として、県自らが家賃と一緒に徴収するという方向へ徐々に切替えが進んでいると承知している。
県が共益費、附属設備使用料を徴収できる項目は、どういった項目なのか。
【県営住宅管理室担当課長(県営住宅)】
県営住宅の共益費、県では附帯設備使用料としているが、これを県で徴収できる項目としては、愛知県県営住宅管理規則において5項目を定めている。
徴収項目としては、一つ目が汚水処理施設に係る電気料、清掃費、消毒費及び消耗品費、二つ目が排水用中継ポンプに係る電気料、三つ目がエレベーターに係る電気料、保守点検費及び消耗品費、四つ目が揚水ポンプに係る電気料、五つ目が、廊下灯、階段灯及び街路灯、その他これに類するものに係る電気料である。
【高木ひろし委員】
県が共益費を徴収する制度になってから5年たつが、県が徴収に移行した県営住宅はどれくらいあるのか。
【県営住宅管理室担当課長(県営住宅)】
県が附帯設備使用料を徴収している住宅は、県営住宅295住宅のうち、令和5年度では93住宅であった。令和6年度に新たに11住宅が県徴収に移行し、現在は、104住宅で県が附帯設備使用料を徴収している。
【高木ひろし委員】
今後、この共益費が、自治会による徴収から県の徴収へと移行が見込まれる住宅はあるのか。
【県営住宅管理室担当課長(県営住宅)】
現在、附帯設備使用料の県徴収への移行に向けて、11の県営住宅の自治会と調整を進めている。これらの住宅が県徴収に移行した場合、令和7年度には、115住宅で県が附帯設備使用料を徴収する予定である。
【高木ひろし委員】
要望になるが、5年、6年たっても自治会徴収から県徴収へ移行が全体の半数も進んでいない。徐々に進んではいるが、このペースはいかがなものかと思う。
私が相談を受けた直近の例でも、ある県営住宅で、自治会の役員を引き受けるか引き受けないかが、住民間でトラブルになっている。自治会からすれば、順番に役員をやってもらっているので、あなただけ勝手な理由で自治会役員をやりたくないというのは駄目だと言って、自治会の役員を引き受けるようにプレッシャーをかけている。ところが、この人は両親が亡くなって一人住まいになり、なおかつ精神疾患を患っているような事情があって受けられない。対人のいろいろなコミュニケーションの問題があるので、一軒一軒回ってお金を徴収する作業は、とても私にはできないと言って固辞しているが、自治会役員からは、その障害があるという事情があるならば、それを証明して周りの人に明らかにしなさい。そうでないと、自治会役員を免れて楽をしているようにとられるから、ほかの人が役員を受けてくれなくなる。こういう理屈で、厳しい問題になり、この人は、結局その住宅を退去せざるを得なくなった。
自治会の話も聞いてみると、大きな県営住宅であり、まだ自治会が徴収しており、かなりの金額を一軒一軒にわたって自治会費と一緒に徴収する仕事を住民自らが担っている。自治としては、美しいような聞こえはあるが、もともと入居している人が、低所得者であったり高齢者であったり障害者であったり、非常にそういう困難な事情を抱えた人がほとんどである。普通の自治会の役員を平等に担えるような人ばかりではない県営住宅の特質を考えれば、一刻も早く自治会の負担を軽減するために、速やかに全戸において、共益費を自治会が徴収するのではなく、県が徴収するという方向に転換を強力に進めてもらうようお願いする。