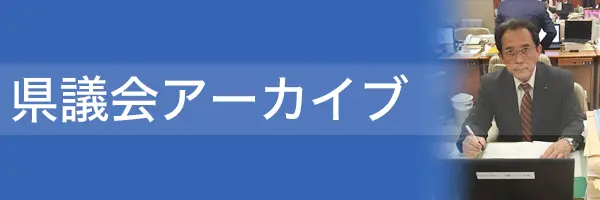【高木ひろし委員】
決算に対する報告書91ページ、14地域生活定着支援センター事業費について、昨年度の支援実績はどのようになっているのか。
【地域福祉課担当課長(地域福祉)】
矯正施設退所後に、住まいの確保や福祉サービスの利用が必要な人の申請支援等を行うコーディネート業務が119人、地域生活を見守るための家庭訪問や施設等への助言を行うフォローアップ業務が84人、福祉サービス等についての相談支援業務が53人等となっている。
【高木ひろし委員】
平成22年4月に、この地域生活定着支援センターが県に設置されており、以後15年がたち、ほぼ同じ事業者に継続して1年ごとに委託されているが、今答弁があったようなコーディネートとかフォローアップの実績だけでは、実質的な中身が把握できない。
この事業の目的にもあるように、刑務所を出所した人が、地域に本当に定着するために、福祉的な支援を行う、支援につなげるという重要な役割であり、端的に言えば、再犯を防止する、再び刑務所に戻るようなことがないようにすることが地域定着だとしている。再犯率が本当にどの程度抑制されたのかが成果を計る上での肝になると思う。
国の犯罪白書によると、満期で釈放された受刑者等が2年以内の再入率、出所後の犯罪によって、受刑のため再び刑事施設に入所した人の割合は、令和3年度においては21.6パーセントといわれている。愛知県の地域生活定着支援センターが支援した人の再入率、刑務所に再び入る人の率はどのようになっているのか。
【地域福祉課担当課長(地域福祉)】
地域定着支援センターでは、家庭訪問や市町村、入所先施設等、関係機関との情報共有により支援対象者の生活状況の把握に努めているが、逮捕された場合に警察等からの連絡がないなど、支援中の逮捕者数や刑事施設への入所者数を正確に把握することが困難である。
このため、質問の再入率についての統計はないが、センターの支援中に逮捕されたことが判明した人は、平成31年4月以降の支援対象者847人のうち88人で、その割合は10.4パーセントとなっている。
【高木ひろし委員】
数字だけ見ると、全国が21パーセントで愛知県では10パーセントで低いように思うが、本当かと感じる。国における数値と同様に、刑務所から出た人をいろいろな福祉施設やグループホームに入ってもらうなど福祉につなげた後2年くらいはフォローを続けて、その後、刑務所に再び入ってしまうような、本当はもっとフォロー期間を長く取ればいいのかもしれないが、愛知県のセンターにおいても、百数十人が保護観察所から紹介をされて、この人々を県内のいろいろな施設に入ってもらった後の2年くらいのフォローアップは必須ではないかと思う。制度上、国に報告義務がなく、センターで把握している数字がないとのことであるので、保護観察所、法務省矯正局や福祉事業者と連携をもっと密にしてもらい、支援対象者に寄り添った支援を続けていってもらうことを要望する。
次に、令和5年度愛知県歳入歳出決算及び美術品等取得基金運用状況の審査意見書28ページに児童措置費負担金という項目があり、未納率が増加している。
児童相談センターの措置によって、施設等に入所した子供の措置費に関する費用を誰が負担するかという話であるが、法律的には保護者負担となっている。この保護者負担を保護者から徴収することが十分にできていない数字だと思う。
この未収率と、未収になってしまう事情はどういうものなのか。
【児童家庭課担当課長(児童家庭)】
児童措置費負担金は、保護者の負担能力に応じ、金額が定められているが、未納となる主な理由としては保護者の生活困窮による場合が多くなっている。
本県では、毎年7月及び12月を納入促進月間として家庭訪問を重点的に行うなど納入指導に努めており、そうした中で個々の世帯の実情を十分に考慮して債権回収を進めている。
特に、虐待により施設入所を要する事案では、一旦施設へ入所した場合であっても、子供が再び家庭で安全に生活できるよう継続的な支援が必要であり、子供の利益を第一に考えると保護者との関係性が重要になるため、強硬な納入指導がなじみにくいことも未収額増加の一因となっている。
引き続き、保護者の負担能力と子供の最善の利益を十分に勘案しながら、適切な債権回収に努めていく。
なお、収入未済の率は、昨年度は約43パーセントとなっている。
【高木ひろし委員】
未収率が4割を超えている事情を聞くと、例えばDV等虐待のおそれがあることで、児相が親から引き離して施設へ入所させて保護する場合に、その費用を引き離した親に負担させないといけないのは、強制的に措置をしている以上、行政が子供の生活や食費にかかるものは負担すべきではないかと思う。法律の建前は保護者に負担させるとなっているため、今の答弁にあったように、最終的には保護者の下に帰すので、保護者との関係性が非常に大事になる。もともと生活困窮によって、子供の安全が脅かされるような事態が発生しているので、費用を引き離している家庭から取ること自体がなかなか難しいと思う。
負担能力の問題や、強硬な納入指導が難しいと指摘があったが、運用の基本となるルール自体、法律的には債権なのかもしれないが、未収債権だから何とか取り立てようという建前の中で運用していることに問題があるように感じる。制度の改善について国に要望するなど検討してもらうよう要望して、質問を終わる。