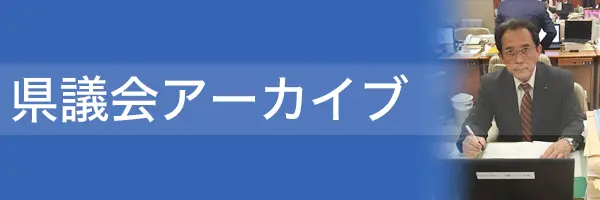【高木ひろし委員】
私からは、県民文化局関係で一点、環境局関係で三点質問する。
まず、報告書の49ページ、10の愛知県国際交流協会運営費補助金について伺う。
愛知県国際交流協会運営費に対する補助金のうち、外国人の生活相談を担う一元的な相談窓口の運営に充てられている経費はどのぐらいになるのか。また、経費の内訳はどのようか。
【多文化共生推進室長】
愛知県国際交流協会運営費補助金1億6,222万4,658円のうち、一元的相談窓口の運営費は、4,236万3,000円で、このうち約86パーセントに当たる3,628万3,000円が相談員の人件費となっている。残りの14パーセントは、窓口で対応していない言語による相談等に対応するための民間通訳会社への委託料が295万2,000円、弁護士相談事業の委託料が70万2,000円、市町村窓口等に配布する相談員向けの手引の印刷製本費36万3,000円などである。
【高木ひろし委員】
私が外国人に対する一元的相談窓口の事業について質問する経緯として、先日、10月7日に、外国人相談に関わる自治体が一元的な窓口を設置する事業に対する国の補助金の予算が不足しており、自治体に満額の補助金が交付されなかったと中日新聞の報道があった。
本県のように県内の外国人が非常に多い県にとっては、特に重要な取組だと思っており、本県における影響が心配される。
この新聞報道によると、令和5年から2年連続で法務省の事業予算を自治体の申請が上回り、今年度は257自治体において、申請どおりの額が交付されなかったようである。
本県の令和5年度の交付額について、影響はあったのか。影響があった場合には、財源不足に対しては、どのように対応したのか。また、国に対してはどのような要望を行っているのか伺う。
【多文化共生推進室長】
まず、本県への影響であるが、交付金の補助率は2分の1で、交付限度額が1,000万円となっており、昨年度は限度額となる1,000万円が交付されたが、今年度申請分は、1,000万円から13パーセントカットされた870万円とする内示が国からあった。
このため、今年度の財源不足130万円については、アルバイトの勤務日数を減らすなどにより対応している。
また、国に対しては、今年7月に行った愛知県の知事要請や、8月の全国知事会による国への要望において、十分な予算を確保するよう求めている。
【高木ひろし委員】
報告書67ページ、先進環境対応自動車導入促進費補助金について伺う。
この補助金は、事業者等が先進環境対応自動車、いわゆるEV、PHV、FCV等を導入することを促進するための補助として、環境局が以前から実施している事業と承知しているが、改めて本県の制度の概要と令和5年度における具体的な実績について伺う。
【地球温暖化対策課担当課長(企画・自動車環境)】
先進環境対応自動車導入促進費補助金は、自動車からの温室効果ガス排出量の削減と大気環境の改善に寄与することを目的とし、EV・PHV・FCV等の乗用車やトラック、バスを導入する事業者等に対して、その導入経費の一部を補助する制度である。
令和5年度の補助金の額は、例えば、申請件数の多い乗用車の例では、EVは上限40万円、PHVは定額20万円、FCVは定額60万円の補助を実施している。
また、補助事業の全体の実績について、補助台数はEV591台、PHV696台、FCV30台など合計1,474台、前年度比114.2パーセント。また、補助額は、約4億3,700万円、前年度比122.3パーセントといずれも前年度を上回る実績となっている。
【高木ひろし委員】
同様の補助は国も実施しており、この上に自治体が上乗せする補助で、環境によい自動車が普及し、地球温暖化防止に貢献するという趣旨であるが、自治体によって、例えば、EVには幾ら、FCVには幾らという金額等にばらつきがある。
本県においては、答弁の中でFCVに一つポイントを置いて、令和6年度からFCVには100万円とかなり大きい額となっているが、これが台数の普及に対して、効果があったのか。
限られた財源であり、環境対応自動車が1台でも多く普及するよう、金額の差を設けていることが効果を発揮しているのか、どのような見解を持っているのか。
【地球温暖化対策課担当課長(企画・自動車環境)】
国が実施しているクリーンエネルギー自動車導入促進補助金、いわゆるCEV補助金は、法人・個人を問わず、EV、PHV、FCVを導入する者に対して補助を行っており、補助上限額は、EVは85万円、PHVは55万円、FCVは255万円となっている。
このCEV補助金に、本県の補助金を上乗せして活用すると、例えば、EVではトヨタのbZ4Xの車両本体価格約500万円に対して、補助額は125万円。また、FCVでは、ホンダのCR-Vの車両本体価格約730万円に対して、315万円の補助を受けることができる。
こういった補助を受けることで、比較される車両との価格差を一定程度補填できることから、EV、PHV、FCVの選択を促すことができた。
この補助金の評価としては、令和4年度の末の統計では、EV・PHV・FCV全体の普及台数について、東京都に次ぐ全国第2位となっており、効果的な補助制度と認識している。
【高木ひろし委員】
今、答弁のあった1位が東京都であり、これは財政力の差が大きいため、東京と同じようにとは、なかなか言いにくい面もあるが、やはり本県は、地球温暖化防止戦略で非常に高い目標数値を設定している。2030年度までに保有台数に関して先進環境自動車が2割になるという非常に高い目標である。
2030年の目標を、この補助制度だけで達成しようとしているわけではないと思うが、やはり個々の購入に対する補助金の効果は、非常に大きい。1位の東京都のレベルに近づくように、私は事業者向けに限定した補助ではなく、個人の所有に対しても補助すべきではないかと思うが、今後の方向性について、補助制度の拡充、運用の考え方を持っているのか伺う。
【地球温暖化対策課担当課長(企画・自動車環境)】
先ほど、本県のEV・PHV・FCVの普及台数は全国第2位と答弁したが、ただいま高木ひろし委員から指摘のあったとおり、あいち地球温暖化防止戦略2030(改定版)の取組指標である2030年度におけるEV・PHV・FCVの保有割合は20パーセントに対して、2022年度末の実績は0.8パーセントにとどまっており、今後さらなる普及加速が必要である。
2020年3月に実施した県民意識調査では、EV等を購入しない理由として、関心がない、車両価格が高い、インフラの環境が整っていないことが挙げられている。
そのため、先進環境対応自動車の普及状況等を踏まえた補助制度の見直しとともに、今年度新たに創設した充電インフラの整備促進のための補助制度の活用をはじめ、法人・個人問わず適用される本県独自の自動車税種別割の課税免除や、県民へのEV等への普及啓発に引き続き取り組むことで、先進環境対応自動車の普及加速に努めていく。
【高木ひろし委員】
次に、報告書の79ページ、狩猟行政費、狩猟免許について伺う。
ニュース・報道等で全国的に狩猟者、狩猟免許を保持して狩りを行うことができる資格を持っている人がどんどん減っている、また高齢化しているという話を聞いている。
最近だと、例えばシカ、イノシシといった有害鳥獣の駆除作業の担い手がいないという話題もあった。
そこで、愛知県においては、狩猟者の数、狩猟免許保持者の状況、この年齢構成や推移がどのような傾向になってるのか。
【自然環境課担当課長(自然環境)】
本県のこの30年間の狩猟免許保持者数の状況について、網、わな及び銃の各猟法を合わせた狩猟免許所持者の延べ人数は、1995年度の約6,000人が2012年度は約4,100人まで減少したが、この10年間は増加傾向にあり、2022年度では1995年度と同程度の約6,300人となっている。
また、狩猟免許所持者の年齢構成は、2022年度では60代以上が39.6パーセント、50代が19.7パーセント、40代が19.1パーセント、30代が14.7パーセント、10代~20代が7.0パーセントとなっている。
推移として、60代以上の割合は、2011年度の67.7パーセントが、2022年度には39.6パーセントとなるなど、近年その割合は減少傾向にある。
【高木ひろし委員】
今の答弁によると、私の心配は杞憂になったかもしれない。狩猟者は増えており、しかも若い世代が狩猟に関して前向きになっていることは、非常によいことだと思う。こうした若い世代の狩猟者を確保するために、県としてはどのようなことを取り組んでいるのか。
【自然環境課担当課長(自然環境)】
県では、仕事をしている現役世代が狩猟免許試験を受験しやすくするための取組として、免許試験を土曜日に1回、日曜日に1回の年2回実施している。
また、狩猟免許の取得を促すとともに、鳥獣捕獲の担い手としての定着を図るため、熟練の狩猟者などを講師として、狩猟の魅力を伝える狩猟普及セミナーを2020年度から開催している。
特に若い世代の狩猟者を増やすための取組としては、県立の農林業関係の高校や農業大学校に職員が出向いて、狩猟制度の社会的役割・魅力を伝える出前講座を2015年度から実施している。
さらに、狩猟免許を取得した人への支援策として、経験の浅い狩猟者を対象に、狩猟を始める際に必要な知識や、わな捕獲の技術について学ぶ、わな捕獲技術向上セミナーを2019年度から開催している。
【高木ひろし委員】
最近クマによる人身被害などがあり、駆除の必要性が叫ばれているが、基本的には、クマと人間は過去からすみ分けというか、共存してきた関係にある。
人間の安全優先だという考え方で無暗に殺処分するのではなく、狩猟者はクマも含めて生態系について十分な知識を持って狩猟していることが前提であるため、駆除する場合でも、わなで捕まえて、安全な本来の生息場所へ移して放獣するなど、専門家による対応が必要である。クマの被害を過剰に恐れ、駆除しろとかいう話ばかりになる傾向について懸念している。
狩猟者を養成して、同時に狩猟者がクマやシカの生態系について十分な理解を持って、行政の施策等に協力してもらえるような関係を築いてもらうよう要望する。
最後に、産業廃棄物に関連したもので、審査意見書の18ページに税目別収入済額の前年度比較において、産業廃棄物税が前年度6億2,000万余円から4億2,000万余円、約67パーセントに落ち込んでいるが、どのような事情によって生じたのか。
【資源循環推進課担当課長(調整・広域処分)】
産業廃棄物税は、県内の最終処分場に搬入された産業廃棄物の重量に対して課税されており、原則1トン当たり1,000円、自ら排出した廃棄物を処分する自社処分場では1トン当たり500円で計算する。
県内産業廃棄物の最終処分量の約3割を受け入れている公益財団法人愛知臨海環境整備センター(ASEC)の埋立処分量は、近年20万トン台で推移している。ASECの納税額に対応する埋立処分量を見ると、令和4年度は約39万トンと大幅に増加しているが、令和5年度は例年と同程度の約24万トンとなっている。その差約15万トン、納税額で約1億5,000万円の減少となっており、このことが令和5年度に税収が減少した大きな要因と考えている。
【高木ひろし委員】
ASECは県の重要な施設であり、これがいっぱいになると、処理する場所をどこかに求めなくてはいけなくなる。
運び込まれる量を計画的にコントロールしながら、行き場所のなくなるような事態が生じないようにすることが必要になる。
キャップ制度を導入したとのことであり、円滑に県内の産廃が処理されていくような形で上手にASECを運用するようお願いする。