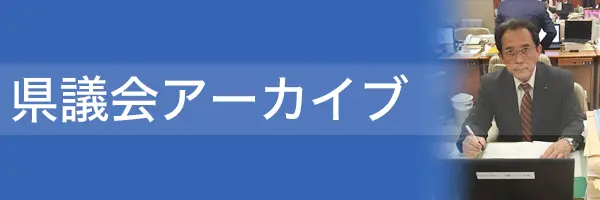【高木ひろし委員】
一般質問でも取り上げたが、旧優生保護法に基づき、本人の意思とは関わりなく強制的に生殖機能を除去する不妊手術を施したことに対して、本年7月に最高裁の判決が確定した。
この法律は国会において、昭和23年に全会一致で制定された。法律そのものが、制定当時から、その前年に制定された憲法の第13条、第14条に違反しているという厳しい認定が確定し、さらには、違法性は認めながらも賠償請求に対しては20年の除斥期間が過ぎているため賠償しなくてもよいという国の主張についても、国が除斥期間を主張すること自体が不正義だと全面的に退けた。これは非常に厳しい判断である。この判決があった後、政府は、原告や被害者への全面的な謝罪と賠償に加え、この根本にある優生思想そのものを克服する取組を行うと宣言し、今、その手続が始まっている。
本会議では保健医療局に答弁してもらったが、本来、これは言うまでもなく非常に重大な人権侵害の事件であるので、この問題に関して改めて、人権行政を所管する本委員会において人権推進課に県の見解を尋ねたい。人権問題としてこの問題をどのように認識しているのか。
【人権推進課長】
本年7月3日の旧優生保護法訴訟の最高裁判決によると、正当な理由なく特定の障害のある人たちを手術の対象にし、障害のない人と区別することは、合理的な根拠に基づかない差別的な取扱いだということであった。本件については、知事が9月18日の定例記者会見で、法律に基づいた機関委任事務として行っていたが、国・県が関わったことは大変重いことであり、大きな人権侵害があったと言わざるを得ないと発言しており、当課としてもこうした不妊手術の強制は、重大な人権問題であったと認識している。
【高木ひろし委員】
本県の人権施策上の今後の取扱いについてであるが、愛知県人権尊重の社会づくり条例と基本計画であるあいち人権推進プランを、我々の委員会が所管する局において推進しているものの、優生思想、あるいは障害者が子孫をつくる権利といったことが、現在のところ、このプランの中に直接的に入っていない。これだけ大きな人権問題として浮上した以上、この人権施策全般を包括する立場で、何らか位置づけし、取り込む必要があると考えるがどうか。
【人権推進課長】
あいち人権推進プランは、条例に基づく基本計画として、人権施策の総合的かつ計画的な推進を図るために全庁を挙げて策定したものである。現在、保健医療局等が中心となって取り組んでいる旧優生保護法に係る人権問題の解消については、高木ひろし委員の指摘のとおり、現在、そうしたプランには含まれていない。
こうした中、今後、国や保健医療局等が用意する啓発資料をあいち人権センターで配架するほか、ウェブページに掲載するとともに、旧優生保護法に係る人権問題の解消に資する啓発用の図書を購入するなど、関係局と連携を図りながら人権課題の解消を図っていきたい。
【高木ひろし委員】
私の一般質問の中で、県立高校で実際に採用されていた高校の保健体育の教科書の記述を紹介した。教育長にも、この問題について学校教育の中で、これから結婚や出産に直面する高校生たちに、どういう考え方を教えていくのか尋ねた。教育委員会としては、教員を中心にした研究会で、実際に起きた不妊手術や、それを受けた人の痛み、思想の問題点などについて具体的に研究し、学校教育の中に生かしていきたいという話も聞き、期待している。
今の答弁にあった、本県が設置するあいち人権センターでの図書の配架やウェブページの記載内容に盛り込むだけではなく、例えば、職員をはじめ一般県民の啓発や研修に、これをどのように生かしていくのか、もう少し補強して答弁してほしい。
【人権推進課長】
当課では、企業で働く人や学校の教職員及び生徒、県内の行政職員など、広く県民に向けて愛知県の人権に関する取組を説明するとともに、日常生活の中にある様々な人権問題全体の話題を通して、人権について考えるきっかけとなるように、人権研修を、昨年度は70回、今年度も8月末までに35回実施している。
今後、こうした人権研修を行う際には、旧優生保護法の下で行われた不妊手術の強制は、重大な人権問題であったことを説明していきたい。こうした取組を進めながら、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指したい。
【高木ひろし委員】
最後に要望する。私も今回この問題を取り上げるに当たって、原告や裁判を支援してきた弁護士など、いろいろな人から話を聞き、資料を読んで、改めてこの優生思想という問題の深刻さを知った。そして、露骨な記載こそなくなったが、実際には、現在もまだ優生思想と思われる、例えば、障害のある人が結婚や出産をしようとしたときに立ちはだかる周囲のいろいろな圧力や障害について知った。特に、原告の尾上夫妻の話を聞くと、一般的に知的障害や精神障害と言われるが、今回、裁判の中で本当に勇気を持って立ち上がった人々の多くは、聴覚障害者である。もともと問題になったときには、聴覚障害者がそれほど多く比重を占めているとは、必ずしも考えられていなかった。
自らの体験があまり人前にさらしたくない話でも、裁判しようと立ち上がって、この不当性を訴える先頭に立ち、一般財団法人全日本ろうあ連盟が組織的に取り組むことで何百件という実例を発掘した。この中には、いわゆる優生保護審査会での審査によって、法令上は強制的ではなく同意という形を取って手術した人が、むしろ主である。裁判として法廷で争われ、最高裁判所が、これは根本的に憲法違反だと認定した対象は、かなり広がっている。旧優生保護法の第4条と第7条の規定が、本人の同意に基づかないで手術した例であるが、それ以外にも、この聴覚障害者の例のように、優生保護法があるために、優生思想に基づいて一応同意という形を取らされて手術をした、あるいは、中絶手術に関してもこの対象に含めると、最高裁判所の判決の影響が今どんどん広がっている。
なので、この根本になる優生思想に関しても、今もなお、例えば、出生前診断の問題などは、命の選別に関わり、どこまでのことが許されるのか。生命倫理上の問題もあって、これは非常に深く影響がある。
片や、過去の例を見ると、近年では、元職員による神奈川県立津久井やまゆり園の障害者の虐殺事件があった。一人の特異な人間の犯罪ではあるが、この元職員は、一番身近で重度障害者の現状を見ていながら、この人たちは、もう生きていること自体が不幸だという独断で勝手な判断をして、あのような虐殺に至った。
その根本には、例えば、かつてのナチスドイツのユダヤ人虐殺は非常に有名であるが、優秀なドイツ民族をこれから繁栄させていこうという考え方の下に、ユダヤ人を虐殺する前の段階で、まず彼らが目をつけたのは実は障害者である。障害者に対し、断種手術はもちろん、障害者自体を抹殺していき、それが結局、ユダヤ人にどんどん拡大されてあの悲劇を生んだ。根本にあったのは優生思想である。
優生思想は一見すると、科学的な根拠を少しでも示されれば、そういう子は生まれないほうがよい、そんな不幸な子はもともと産まないほうがよいのではないかといった方向に行きがちな非常に難しい問題を抱えている。単に本人の同意もなく手術をしたのはいけないというだけの話ではないという意味で、優秀な民族、優秀な子孫を残そうという意図が、そのような極端な悲劇につながったことまで遡って、その影響の恐ろしさ、危険性を相当深く理解しないといけない。
これは、本当にいろいろな実例や映画もある。新川の近くで聴覚障害者の連盟がつくった沈黙の50年という映画の上映があったので、私もそれを見に行ったが、本当にショックを受けた。聾学校に通いながら、聴覚障害同士で結婚することも結構多い。それに対して、結婚までは阻止できないが、出産する、子供をつくることに対して、いかに周りからの強制があって、泣く泣く同意という形で不妊手術をしたという話が、映画の中ではいろいろな人の実例で赤裸々に描かれていた。こういった視聴覚教材もいろいろあるので、そういったものを幅広く収集して、特に若い人たちの心に本当に届くような啓発に取り組んでほしい。