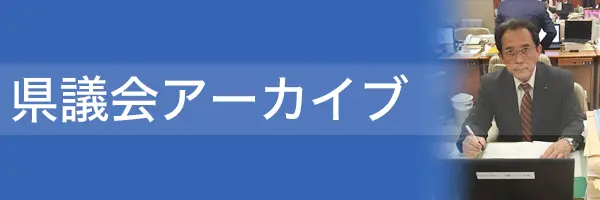【高木ひろし委員】
それでは、私から二点伺う。
まずは、有機フッ素化合物(PFAS)の問題である。
私は当委員会に昨年も所属し、年間を通して何回か尋ねてきた。そして、昨年は、環境省の全国調査が大きな話題を呼んで、NHKがこれを取り上げたことをきっかけにして、非常に一般の関心が高まった。本県議会でも令和5年12月定例議会で、PFAS対策を国において強化することについて意見書が提出された。
今日は新しい年度に入って、PFASをめぐる動きについて総括的にまずは伺う。
国においては中央環境審議会において検討が行われてきて、暫定指針値に関わる国の最近の動きについて、5月頃に動きがあったと聞いているが、どのように県として承知しているのか教えてほしい。
【水大気環境課担当課長(水環境)】
環境省では2023年1月から、PFOS・PFOAに係る水質の目標値等の専門家会議において、ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の暫定指針値の取扱いについて検討を行っている。
その後、2024年6月に内閣府食品安全委員会からPFOS、PFOAについて、ヒトが一生涯にわたって毎日摂取し続けても健康への悪影響がないと推定される1日当たりの摂取量である耐容一日摂取量が設定されている。
その後、2回専門家会議が行われ、その結果を踏まえて中央環境審議会での審議が行われて、本年5月8日に暫定指針値を指針値とする答申がなされている。
その指針値の値については、食品安全委員会が設定した耐容一日摂取量を基に算定すると、PFOS、PFOA、それぞれ50ナノグラムパーリットルとなるところ、暫定指針値の場合と同様に、より安全側の観点から、PFOS、PFOAの合計値として50ナノグラムパーリットルとされている。
環境省において、この答申を受けて指針値の設定等について近日中に各都道府県等宛て通知する予定と聞いている。
【高木ひろし委員】
暫定が取れて指針値になった。また、PFOA、PFOSのそれぞれの基準値だったところ、合計してパーリットルで50という数字が示されたことは、全体として監視の目を厳しく設定する方向で国も動いていると承知した。
次に、本年も4月25日に令和5年度の公共用水域の水質測定結果と地下水質測定結果を国がまとめて公表している。この中で、県内の地点における両物質の検出結果、暫定指針値を超過した地点における対応などについて聞きたい。
【水大気環境課担当課長(水環境)】
本県では、水質汚濁防止法の規定により策定した水質測定計画に基づいて、2021年度から県内の公共用水域及び地下水におけるPFOS及びPFOAの存在状況を把握している。
2023年度においては、名古屋市等の政令市も含めて、公共用水域60地点、地下水35地点の合計95地点でPFOS及びPFOAの調査を実施し、河川1地点、地下水1地点の合計2地点で暫定指針値を超過した。超過したのは、公共用水域である半田市内の阿久比川半田大橋で54ナノグラムパーリットル、地下水では、春日井市内の地下水で130ナノグラムパーリットルである。
暫定指針値を超過して検出された場合の対応としては、環境省が作成したPFOS及びPFOAに関する対応の手引きに基づいて適切に対応している。
具体的に言うと、半田市内の阿久比川半田大橋については、県の2021年度の調査で暫定指針値を超過しており、この阿久比川には水道水源がないため、飲用による暴露防止のおそれがないことから、2022年度以降、継続して調査を行っているところであって、2023年度においても暫定指針値を超過したものである。
春日井市の地下水については、春日井市が2022年度に水道水源井戸の一部の原水で暫定目標値を超過したため、周辺の井戸6地点の水質調査を実施し、そのうち1地点の井戸で暫定指針値を超過した。それから、春日井市は周辺の井戸所有者に対して井戸水の飲用を控えるように注意喚起するとともに、2023年度以降、周辺6地点の継続調査を実施しており、2023年度においても2022年度と同じ井戸で暫定指針値を超過したものである。
【高木ひろし委員】
要注意な地点の紹介があったが、特に気になるのは春日井市である。春日井市は連続して大きく基準値を上回る検出がされていて、まずは飲料水として地下水が人体に摂取されて影響を与えるおそれがあるのかないのか。それから、もう一つは、連続して高濃度の値が出たことは、一体どこから春日井市の地下水に対して流入したのか、健康への被害の防止の話と、排出源が一体どこなのかという両面で、地元の関心が高まるのは当然だと思う。ここは県民環境委員会なので、私が昨年も言ったのは、やはり環境局としては愛知県環境調査センターという非常に優秀なスタッフと、非常に高レベルの検出の装置を持った機関を有しているので、顕著な例である春日井市における汚染の原因が何かと、汚染源は何なのか突き止めることを願ったはずだが、これについて具体的に何か進展、分かったことはないか。
【水大気環境課担当課長(水環境)】
春日井市は、水質汚濁防止法で定める政令市であって、春日井市が調査を行うとともに、原因究明に係る対応を行っているが、聞いているところによると、初めて超過の事例が分かったときに、周囲の事業所等を確認したが、原因は不明と聞いている。
その後、超過した地点の状況を継続して調査していると聞いている。
【高木ひろし委員】
環境局として、県の専門的なスタッフ、調査・分析機能をフルに生かして、春日井市に協力して、汚染源の特定と対策を進めてもらうようにお願いする。
次に、PFASに関して、世間の関心が高まると同時に、私のほうにもいろいろと問合せをもらっていることを一つ聞きたい。このPFOS、PFOAは、30年、40年ぐらい前に、アメリカのデュポンというメーカーが開発した。PFOA、PFOSという人為的に合成された物質には撥水性、水や油をはじく特性があるものだから、まず、デュポン社が商品化したものが、焦げつかないフライパンである。それから、撥水スプレーなどに入れるとか、PFOA、PFOSを混ぜた泡消火器は非常に消火能力が高いというところが代表的な使用方法だと伝えられている。気になるのは、どこの家庭にもあるフライパンの中で、テフロン加工されているものは焦げつかないフライパンとして大いに人気があった。フライパンに使用されるようなPFOS、PFOAは、既に発がん性物質として製造も禁止されているが、現在市中に出回っているフライパンや、撥水スプレー、生活の身の回りの品においてPFOS、PFOAの使用状況はどのように理解すればいいのか。この危険性についてはどのような認識を持って県民生活に当たればいいのか。
【水大気環境課担当課長(水環境)】
PFOS、PFOAについては、高木ひろし委員も示すとおり、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律、いわゆる化審法で、PFOSは2010年、PFOAは2021年に製造、輸入等が原則禁止されている。
身の回りの製品については、環境省が2024年度に取りまとめたPFOS、PFOAに関するQ&A集があって、それによると、家庭の身の回りの製品のうち、フッ素コートされたフライパン、それからフッ素系の撥水スプレーにはPFOS及びPFOAは使用されていないとのことである。
また、そのほかの身の回りの製品について、PFOSは製造等の禁止前を含め、日本国内で製造に使用された報告はない。それから、PFOAは、禁止前はカーペット等の繊維に一部使用されていたが、これらの製品を使用しても心配されるようなレベルのリスクはない。
【高木ひろし委員】
話を聞いてやや安心したが、このPFOS、PFOAに関しては、まだ完全に危険性の範囲が確定したわけではないと思う。また、非常にたくさんの種類のあるフッ素有機物の種類の中で、PFOS、PFOAが限られた2種類なのだが、そのほかの物質が全部安全なのかというと、これも立証されているわけではなく、研究過程にあるものと理解している。
日々、いろんなニュースに接すると、ヨーロッパでは、環境基準がどんどん厳しくなる方向である。最近の報道では、イタリアで日本企業も出資しているような会社が刑事罰を受けるような、PFOS、PFOAの漏出事例も伝わってきているので、これは今後も監視を怠らずに、最新の研究結果などにも常に注目を払って、今後もチェックを続けていきたいと思っているので、よろしくお願いする。
それでは、もう一つのテーマに移る。リチウムイオン電池の適正処理に関してである。
最近、これもテレビ等やマスコミ等で取り上げられて大きな話題を呼ぶようになった。市町村のごみ処理施設や、ごみ収集車のリチウムイオン電池が原因となる火災事故の発生が非常に多く伝えられている。県内の市町村における、リチウムイオン電池が原因となる火災等の発生状況はどのようになっているのだろうか。また、なぜリチウムイオン電池が原因となる火災が発生するのか説明してほしい。
【資源循環推進課担当課長(循環・一般廃棄物)】
国の調査結果によると、リチウムイオン電池が原因とされる火災のうち、職員や消防隊が消火した火災は、全国で2023年度に8,543件発生し、2022年度の4,260件から倍増するなど、年々増加傾向にある。
このうち本県では、2022年度に240件、2023年度に292件が発生している。このほか、出火したものの初期消火された事案や煙が発生しただけの事案などを含めると、さらに多いと考えられる。
火災の原因についてだが、リチウムイオン電池は衝撃が加わると破損して発熱、発火する特徴があることから、ごみ収集車やごみ処理施設で圧縮、破砕されることで発火し事故につながると言われている。
こうしたことが発生するのは、リチウムイオン電池を使用した製品かどうかが外見からは分かりにくいものも多いことから、県民が排出の際、気づかずに不燃ごみなどに混入させてしまうことも原因の一つと考えられる。
【高木ひろし委員】
現在はこのリチウムイオン電池の回収処理については、一般的にどんな仕組みになっているのか。
【資源循環推進課担当課長(循環・一般廃棄物)】
事業者による回収と市町村による回収の主に2通りの回収が行われている。
事業者による回収としては、製品製造事業者や輸入販売事業者により構成された一般社団法人JBRCが、機器から取り外されたリチウムイオン電池について、家電量販店などの協力店で回収しリサイクルを行っている。
また、市町村による回収は、リチウムイオン電池そのもののほか、それを使用した製品も含め、一般廃棄物として通常の回収を行っているほか、家電量販店やホームセンターなどに持ち込んでもらう方法でも回収している。
【高木ひろし委員】
こうした火災事故を防ぐために、市町村ではどのような取組が行われているのか。
【資源循環推進課担当課長(循環・一般廃棄物)】
市町村においては、住民に対し、リチウムイオン電池の危険性や廃棄時の適切な分別について周知を行っている。特に火災が発生した市町村では、被害の状況や原因となったものの写真の掲載などにより啓発を行っている。
また、ごみ収集車両で収集するときに他のごみと区分けして積載する、作業員が手作業によりリチウムイオン電池を抜き取る、発火時に備えて収集車両に消火器を搭載するなどにより対応している。さらに、作業員により、ごみ処理する前のリチウムイオン電池等の抜き取りやごみ処理施設や保管場所に火災検知器、赤外線カメラ、スプリンクラー等を設置することなどで対応しているところもある。
加えて、瀬戸市のように、スプレー缶の排出区分であった発火性危険物にリチウムイオン電池を含めるよう区分変更するとともに、住民の利便性も高めるために、スーパーマーケット、ホームセンター等への持込みに加え、ごみステーションの回収も実施するよう、回収体制も変更した市町村もある。
【高木ひろし委員】
市町村の取組やスーパーマーケット等の事業者の取組を紹介してもらったが、県としては、この問題についてどのような取組を行っているか。
【資源循環推進課担当課長(循環・一般廃棄物)】
リチウムイオン電池による火災事故により、ごみ処理施設が稼働停止になる事案も見られることから、県としても喫緊の課題として認識している。
このため、市町村に対して、令和7年4月に国からリチウムイオン電池の適正処理に関する通知があったが、そうした最新情報を随時情報提供することはもとより、8月に開催する市町村向けの会議において、先ほどの瀬戸市の取組を含む市町村向けの対策事例集を紹介するなど、リチウムイオン電池の適正な処理について周知、助言を行う予定としている。
県民向けには、ウェブページやリーフレット等の様々な媒体を通じて、リチウムイオン電池を適切に処分するよう周知啓発を行っている。なお、来月には、県環境局が発行する環境かわら版に記事を掲載する予定としている。
国に対しては、2024年12月に都道府県、政令市、中核市で構成する全国環境衛生・廃棄物関係課長会から、業界による回収の仕組みの一層の拡充と強化や、処理施設において機械分別できる装置の開発などについて要望を行っている。
今後も国の動向等を注視しながら、適宜、市町村への情報提供、県民への周知啓発を行うとともに、引き続き機会を捉えて国への働きかけを行っていく。
【高木ひろし委員】
最後に要望する。
この問題については、本定例議会としても、意見書を国に提出する動きにもなっているので、国への働きかけも強化してもらいたい。また、私が記事をいろいろ探していて注目したのは、リチウムイオン電池を組み込んだ製品が次から次へと出てくるので、一体どのような装置にリチウムイオン電池が内蔵されているのか、それは取り出せるのか、それとも取り出せないのか、あまりに製品の種類が多いために、しかも輸入品なども相当あるから、なかなか分別が大変だということである。これに対しては、現場の作業員が本当に手仕事で、目視でもって開けているのが現実である。これをもう少しシステマチックに分別できないのかという研究が幾つか進んでいて、二つ紹介する。IHIのグループ会社である株式会社IHI検査計測という横浜の会社はAIを使って、赤外線の透視でもっていろんなごみに交ざった中にリチウムイオン電池を含む製品らしきものを発見して、AIが判定する。これは恐らくリチウムイオン電池が含まれている、例えば携帯扇風機ではないかと赤外線の透視で見て、空港の保安検査のような装置により、AI判定で見つけ出すというものがあって、結構な効果を上げているようである。ただ、これは100パーセントではない。AIが認識した、このような製品にはリチウムイオン電池が含まれているという情報をたくさん集積して、それに当てはまる形状のものがあるかないかをAIが判定してくれるわけだから、計測チェックミスを行ってしまうことも間々あるとは聞いている。
それと、全く別の方法として、埼玉県本庄市にあるエムケー工業株式会社という精密プレス業が開発している仕組みは、電池だから、放電をさせて発火を抑制するというものである。つまり、全部放電してしまえば、リチウムイオン電池の危険性はなくなるわけである。だから、放電を促進させて発火を抑制することを分別過程で行うという。そして、放電できない危険な電池は分別しつつ、放電を促進して無害化する装置だそうであるが、これも非常に注目されると思う。
こうしたノウハウを持った企業が、リチウムイオン電池の処理に関する新技術を次々と開発中であるので、大いに注目して、この活用促進、普及に努力することも大事な観点であろうと思う。とにかく消防の人や、環境事業所の市町村の人にとっては、危険が身近に迫っている事案であるので、早急にこのような心配がなくなるように対策を進めることを願う。